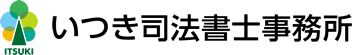みなし相続財産についてわかりやすく解説! 具体例や計算上の注意点など紹介
相続税が課税されるのは遺産だけではありません。実質において遺産の受け取りと同視できる財産については「みなし相続財産」の枠組みに入り、相続税が課税される対象になります。純粋な相続財産以外にも課税対象が広がりますので、相続税の計算をするときは注意が必要です。
具体的にどのようなものがみなし相続財産となるのか、どうやって相続税の計算をするのか、ここで解説していきます。
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、「相続財産ではない金銭等ではあるが、相続税が課税される財産としてみなされた財産」のことです。
基本的には相続や遺贈で取得した財産を調べてその価額を基に相続税を計算するのですが、それ以外の財産であっても、特定の状況下で金銭や権利を取得した方は相続税の計算をしなければなりません。
これは何もみなし相続財産に限った話ではありません。
例えば相続と遺贈のどちらでもない「死因贈与」により受け取った財産も相続税の計算対象です。「相続開始前3年以内の贈与財産」、「相続時精算課税の適用を受けた贈与財産」も同様です。
なぜ相続税を課税するのか
純粋な遺産に限定せず、みなし相続財産の枠組みを設けているのは、「相続税の納税者間で不平等が生じないようにするため」です。
みなし相続財産として扱われる財産は、いずれも相続により取得する被相続人(亡くなった方)の財産と近い性質を持ったものです。保険契約の仕組みなどを利用して、過剰に税負担を回避することを防ぐ役割を果たしているのです。
みなし相続財産の処理・課税の方法
みなし相続財産はあくまで課税上の話であり、相続財産と同じように遺産分割まで行うわけではありません。契約などに基づいて受取人は決まっていますので、「その金銭はみなし相続財産だから相続人みんなで分け合う」といったことは行いません。
また、相続財産ではないことから遺留分の計算からも原則として外れます。
※遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に最低限留保される遺産のこと。遺留分として認められる額が受け取れていないときは遺留分の侵害があったとして「遺留分侵害額請求」を行うことができる。
そのため少額しか相続人が受け取れていなかったとしても、みなし相続財産を得た方に遺留分侵害額請求をすることはできません。
※相続人との間で著しい不公平があり、その差を是認できないような状況だと、例外的に相続財産への持ち戻し対象となり得る。
なお、相続税の負担については「友人などの第三者や被相続人の兄弟姉妹、祖父母、内縁の配偶者などは税額が2割増しになる」という点に注意しましょう。みなし相続財産に限らず適用されるルールですが、契約により身近な家族以外が受取人になっているときは想定より大きな税負担を負うおそれがあるため要注意です。
みなし相続財産に該当する例
みなし相続財産に該当する例は多くあります。
- 生命保険金
- 生命保険契約に関する権利
- 死亡退職金
- 定期金や定期金に関する権利
- 特別縁故者への財産分与
- 特別寄与者への特別寄与料
- 債務免除による利益
- 信託に関する権利
- 教育資金や結婚子育て資金の一括贈与の特例に関する管理残額 など
生命保険金について
代表的なみなし相続財産が「生命保険金」です。特定の条件を満たす場合にみなし相続財産となり、相続税が課税される場合でも一定額を差し引いて残った額にのみ課税されます。
《生命保険金に相続税が課税される条件》
- 被保険者:被相続人
- 保険料負担者:被相続人
保険金の受取人が保険料も負担していたのであれば相続財産と保険金に関係はなく、相続税は課税されません。しかしながら相続税以外の税に注意が必要です。この場合においては所得税が課税されます。被相続人以外の保険料負担者、さらに他人が受取人であるときは贈与税が課税されます。
《課税金額の計算方法》
非課税枠の額 = 法定相続人の数×500万円
相続税の計算に含める金額 = 生命保険金-非課税枠の額
つまり生命保険金の額が1,500万円あるときでも、法定相続人が3人いるときは非課税ですべて受け取ることができます。法定相続人が2人であるときは500万円を相続税の計算に含めます。
法定相続人の数に応じて節税効果が得られますので、相続税対策として生命保険契約が利用されることもあります。
死亡退職金について
「死亡退職金」とは、被相続人が亡くなったときに支給される退職金のことです。こちらも特定の条件下でみなし相続財産となり、生命保険金同様に非課税枠が設けられています。
《生命保険金に相続税が課税される条件》
- 退職金の支給される会社に被相続人が勤めていた
- 被相続人が亡くなってから3年以内に支払いが確定した
存命中に退職金を受け取っていたのであればその当人に所得税が課税されますし、亡くなってから3年を過ぎて支給が決まったときは受取人に対して所得税が課税されます。
《課税金額の計算方法》
非課税枠の額 = 法定相続人の数×500万円
相続税の計算に含める金額 = 死亡退職金-非課税枠の額
非課税枠の計算方法は生命保険金と同じです。法定相続人がいることにより非課税で受け取れることもあります。
定期金について
生命保険金や死亡退職金は、ある方が亡くなったことをきっかけに、一括で支払われる金銭です。しかし個人年金のように定期的に繰り返して支給される金銭もあります。「定期金」と呼ばれ、これもみなし相続財産になります。
また、定期金の受け取りが実際に行われていない状況でも、「定期金に関する権利」を得たときはその権利がみなし相続財産となるケースもあります。被相続人が掛金・保険料の負担をしていたなど、所定の条件を満たすときは、被相続人が負担していた金額が受取人のみなし相続財産として相続税の対象になります。
国家公務員共済組合法や地方公務員等共済組合法など、法令に基づいて支給される遺族年金も定期金に関する権利ですが、こちらはそれぞれの根拠法で非課税規定が設けられていることが多いです。契約ではなく法令に基づいて支給されるものについては、みなし相続財産にならないことがありますので留意しましょう。
「何がみなし相続財産になるのか」「いくら相続税の計算対象になるのか」など、分からないことは相続税に精通したプロに相談して解決していきましょう。
よく検索されるキーワード
司法書士紹介

代表司法書士 武田一樹
私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。
当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?
お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。
-
- 所属団体
-
東京司法書士会(登録番号3502)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
-
- 経歴
-
平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
事務所概要
| 事務所名 | いつき司法書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502 |
| 電話番号 | 0422-24-7924 |
| FAX番号 | 0422-24-7925 |
| 受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
周辺マップ