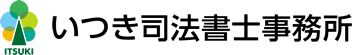遺言書 相続放棄
- 相続手続の流れ ~死亡届や遺産分割協議、財産の名義変更や相続税の申告など~
もし借金の存在が明らかであり、その大きさが資産を上回っているのであれば、「相続放棄」をすることも検討すべきでしょう。 ただ、相続人に十分な資産があり多少の借金を肩代わりしてでも被相続人の財産が欲しいという場合には、「単純承認」として相続を受け入れることも選択肢に入ってくるかもしれません。単純承認をする場合特に行う...
- 遺産を渡す方法「特定遺贈」について| 包括遺贈や特定財産承継遺言との違いなど
相続人であれば相続によって自動的に遺産を承継することができますし、そうでなくても遺言書により遺産を取得することができます。 遺言書を活用する場合にもさらに特定遺贈や包括遺贈などいくつかのパターンがあり、それぞれの効力について知り、最適な手段を選択することが重要といえます。ここでは特に「特定遺贈」に焦点を当てて、包...
- 遺産分割協議のポイント! 協議の準備や進め方、遺産分割協議書の作成方法について
明らかにリスクが大きいと判断できるときは「相続放棄」を検討します。 財産関係、権利義務関係が複雑で相続をすべきかどうかの判断が難しい場合は「限定承認」という選択を取ります。限定承認をした場合、仮に消極財産の方が割合大きかったとしても、弁済の責任は相続財産の範囲にとどめることができます。つまり、相続人個人の資産を換...
- 司法書士に相続問題を相談・依頼するメリットとは
特に相続放棄(一切の財産を相続しないための手続き)や限定承認(プラスの財産の範囲内でのみ責任を負うとする相続の方法)の判断は今後の手続き内容を大きく左右する問題ですので専門家による助言が重要な意味を持ちます。遺産調査のサポート遺産相続を進めるには、前提として現金・預貯金・不動産・有価証券などすべての遺産を把握して...
- 遺言書には必ず従わなければいけないの?相続放棄は可能?
遺言書は、亡くなったひとの意思が書かれた大切な書類です。しかし、そこに書かれている内容に必ず従わなければならないのか、疑問を持つ方も少なくありません。また、相続したくない場合に「相続放棄」ができるのかも気になるポイントです。今回は、遺言書の効力や相続放棄の仕組みを見ていきます。遺言書の効力とは遺言書は、民法で定め...
- 相続問題で司法書士に依頼できること
相続問題でお困りの場合、司法書士に依頼できることとしては、①遺言書の作成・保管、②遺言書の検認申立書の作成、③遺言の執行、④遺留分侵害請求の内容証明郵便の作成、⑤遺産分割協議書の作成、⑥相続手続きの代行があります。 ■遺言書の作成・保管遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。自筆証...
- 相続放棄の手続きについて
■相続放棄の効力相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示のことをいいます。相続放棄を行った場合、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の権利・義務を一切相続しないことになります。相続放棄が行われることが多いのは、被相続人の相続財産が合計でマイナスとなってしまう場合や、相続し...
- 相続登記とは
また、遺言書がある場合には遺言書が、遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書が必要となります。不動産トラブルを避けるため、遺産の分配方法が決まったらすぐに相続登記を済ませるようにしましょう。 いつき司法書士事務所では、東京都武蔵野市、杉並区、世田谷区、三鷹市、練馬区にお住まいの方を中心に法務相談を承っております...
- 遺言書の種類と効力
■遺言書の種類遺言書は、普通の方式と特別の方式の2つに大別されます。このうち特別の方式は非常事態の際に認められる遺言方式であり、現在ではほとんど利用されていません。普通の方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。 〇自筆証書遺言自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する遺言方式です...
- 公正証書遺言の作成に必要な書類
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書のことを指します。公証人が関与することで、遺言書作成における不備で無効になることや紛失を防ぐことなど多くのメリットがあります。しかし、自身で作成する遺言書と異なる点として、適切な手続きを踏まなければならないことが挙げられます。ここでは、公正証書遺言の作成に...
- 遺言書の検認手続き|手続きの流れや必要書類など
■遺言書の検認手続き遺言書は、大きく3つに分けられます。具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言であり、被相続人の死亡時に遺言書が見つかった際に検認手続きが必要になるのは、自筆証書遺言です。 自筆証書遺言とは、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押す遺言書のことです(但し財産目録について...
- 相続の対象になる財産とは? 相続対象外の財産や注意が必要な財産など紹介
価値ある不動産がある場合でも、それ以上の負債があれば相続放棄も検討することになるでしょう。 相続対象外の財産亡くなった方が持っていた権利や義務はすべて相続対象になるのが基本ですが、以下に示すものに関しては対象外です。 被相続人の一身専属権相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。...
- 不動産を家族信託する方法とは
不動産を信託財産とした家族信託を契約した場合、不動産を継承する人を指定することができるため、遺言書の作成と同様の効果を得ることができます。 ただし、家族信託の契約は、その次以降の世代まで不動産を相続させる順位を指定することができますが、遺言書の作成の場合は、1世代までしか不動産を相続させる順位を指定することはでき...
- 公正証書遺言の効力|無効になってしまうのはどんなケース?
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。中でも公正証書遺言は、公証人に作成してもらうため、一番確実性や信頼度が高く、効力の高い遺言書といわれています。その効力が高い公正証書遺言であっても、無効になってしまうケースがあるのです。今回は、公正証書遺言が無効になってしまうケースに...
- 投資信託の相続|名義変更手続きなどの流れを解説
しかし、投資信託は、遺言書により相続人が決まっていない限りは、例外的に遺産分割により相続人が決定します。 このように、遺産分割により相続人が決定された投資信託は、どのように相続手続きをすればよいのでしょうか?今回は、投資信託の被相続人からの名義変更手続きの流れについて解説していきます。 投資信託の名義変更手続きの...
- 相続財産に借金があった!相続放棄の手続方法と流れとは?
そんなときに検討するのが“相続放棄”です。 相続放棄をすることで相続人としての立場を捨てることができ、相続によるリスクも回避することができます。ここではこの相続放棄をするための手続の方法、流れについて説明していきます。 相続放棄をするまでの流れ被相続人が借金をしていたことが発覚してから、相続放棄をするまでの流れを...
- 【相続登記の義務化】開始時期や罰則、過去の相続について解説
相続に関するお悩みはいつき司法書士事務所へご相談ください いつき司法書士事務所では、相続・遺言書に関するご相談を承っております。相続登記手続きをはじめとする、相続に関するお悩みがおありの方は、いつき司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
- 遺留分とは?留保できる相続財産の割合や権利者の範囲、請求方法について
遺言書の作成により被相続人は自らの財産を好きに他人に与えることができるのですが、この場合でも特定の相続人には遺留分として財産が留保されています。 遺留分とは何か、どれだけの財産が留保されるのか、基本的なルールから請求の方法までここで解説していきます。遺留分とは遺留分とは、「遺贈などがあった場合でも遺留分権利者に留...
- 公正証書遺言について~効力や特徴、自筆証書遺言との違い~
記載できる遺言に違いはありませんが、遺言書の有効性について争いが起こる可能性なども考慮して選ぶことが大事です。そこで当記事では代表的な上記2種の遺言書につき比較検討ができるよう、特に公正証書遺言へ焦点を当てて解説をしていきます。公正証書遺言とは公正証書遺言は、「公証人に遺言内容を伝えて遺言書を作成してもらう」とき...
- 相続人調査にかかる費用の相場は?自分で行うことは可能?
相続・遺言書に関することはいつき司法書士事務所へご相談くださいいつき司法書士事務所では、相続・遺言書に関するご相談を承っております。相続人調査をはじめとする、相続に関してお悩みがおありの方は、いつき司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
- 包括遺贈についての解説| 遺贈とは何か、特定遺贈との違いや特徴など
亡くなった方の財産は基本的に一定の身分関係を持つ相続人が取得しますが、遺言書を作成すれば第三者へ譲渡することも可能です。この遺贈にはさらに種類があり、特定の財産を指定してする遺贈と取得割合を定めてする遺贈があります。 それぞれに特徴が異なりますので、相続対策を取るときは遺贈の仕組みについても知っておくことが大切で...
- 不動産の共有名義人のいずれかが死亡した場合の相続手続き
遺言書の有無を調べる遺産相続の対象になる不動産を特定する相続人を確定する遺産分割協議を行う遺産分割協議書を作成する相続登記を行う遺言書の有無を調べる共有名義人のどちらかが亡くなった場合、遺言書の有無を調べます。遺言書が見つかれば内容に従って手続きを行いますが、遺言書には以下の3種類があり、中には注意が必要な遺言書...
- 【司法書士が解説】認知症の人が書いた遺言書に効力はある?
遺言書は死後に自らの意思を伝える手段として、被相続人が生前中に作成します。この記事では、認知症の人が書いた遺言書に効力はあるのかという疑問について解説します。認知症の人が書いた遺言書の効力は遺言能力の有無によって判断される認知症の人が書いた遺言書は、遺言書作成時の「遺言能力の有無」によって判断されます。遺言能力と...
- 遺言書の保管方法を解説|自宅・貸金庫・公証役場・法務局での保管について
遺言書を作成するときは無効とならないよう気を付けないといけません。そして作成するだけでなく、保管場所についてもよく考えなくてはなりません。 適切に保管ができていないと、期待通りに遺言が実行されないリスクが高まってしまうからです。ここではよくある保管場所について取り上げ、それぞれの利点や問題点などを解説していますの...
- 遺産相続の3つの方法とは|効力や手続方法、注意点を比較
単純承認・限定承認・相続放棄の3つ遺産相続の方法は、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3つに分けられます。 このうち①と②に関しては「相続の仕方」に違いがあり、これらと③には「相続をするかどうか」という違いがあります。 それぞれの効力や手続方法、注意点などを以下で比較しながら解説していきます。効力の比較効力の比...
- 遺贈手続きの流れと遺言内容の検討をするときのポイントについて
「遺贈」とは遺言書を使って財産を与える行為をいい、遺贈をすることで相続人以外にも遺産を取得してもらうことが可能となります。 そこで遺贈を実行するには遺言書の作成が欠かせません。遺言書の種類を決めて、民法という法律に従い、決められた方法で遺言書を作らなければいけません。 遺言書に記載する遺言の内容についてもよく考え...
- 相続人の調査| 集める戸籍の種類や取得方法、その他相続手続で調査が必要な事項
相続開始後、相続人のほかにも「遺言書の有無と内容」「遺産の内容と価額」について調査を行う必要があります。これら調査事項についてそれぞれ簡単に解説していきます。遺言書の有無と内容遺言とは死後に効力を生じさせる目的で残しておく意思表示のことで、これを書面化したものが「遺言書」です。 遺言書が作成されているときは遺産分...
- 相続財産の調査方法や各種書類取得にかかる費用について
相続が開始されると、相続放棄の判断をするため、遺産分割をするため、相続税の申告をするために相続財産の調査が必要です。当記事で基本的な相続財産の例を挙げ、調査の方法を説明していきます。また、調査にあたり費用がかかることもありますので、その点についても言及します。相続財産の範囲亡くなった方が持っていた財産は広く相続の...
- 遺言書作成の流れと必要書類、作成費用について
法的効力を持つ遺言書を作成するためには、法令に則って作成する必要があります。作成方法に対応して遺言書にも種類があり、それぞれ必要な書類や費用も異なります。 遺言書というものを知っていても、正しい作成の方法を把握していない方がほとんどです。そこで当記事では代表的な遺言書(自筆証書遺言と公正証書遺言)について、具体的...
- 遺言書の種類| 作成方法や費用、メリット・デメリットを種類別に解説
遺言書には種類があります。その種類に応じて作成方法は異なり、決められたルールに従って作成をしなければ無効になってしまいますので注意が必要です。そこで、この記事では遺言書の種類別に作成方法を解説します。特に代表的な遺言書である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」については、近年の法改正の影響や費用など、詳細も併せて紹介...
- 認知症に備える相続・遺言対策について解説
人で贈与契約を交わすこともできなくなり、遺言書を作成することもできなくなってしまいます。 このとき、成年後見制度の利用によって当人を法的に支援することはできますが、同制度が目的としているのは当人の権利・財産を守ることです。そのため財産を減らすことになる贈与をすることは基本的にできません。また、遺言書の作成は一身専...
- 遺言書作成前に知っておきたい遺言執行の基礎知識
遺言書を作成するとき相続人への財産の分配方法に注目しがちですが、遺言書の内容を実現するためには「遺言執行」について理解しておくことが大事です。これは遺言者の意思を実現する重要な手続きであり、遺言執行が適切に行われなければせっかく作成した遺言書も意味をなさなくなってしまいます。 そこで当記事では、遺言書を作成する前...
- 後見制度で将来に備える|後見人の種類とそれぞれの利用シーンとは
遺言書の作成 など補助人比較的軽度の判断能力の低下が見られる方を支援するため、「補助人」が選任されます。 例えば初期の認知症の方、知的障害・精神障害などにより日常生活はおおむね自立して行えるものの、高額な取引や不動産の売買など重要な法律行為を行う際には判断能力の面で不安が残るといったケースが該当します。 基本的に...
- 法定相続人の相続割合とは?基本的な仕組みを具体例で解説
遺言書がある場合の法定相続分遺言書が作成されている場合、法定相続分より遺言内容が優先されます。 法定相続分はあくまで目安であり、そもそも遺言がなくても強制されるものではありません。一方で法的に有効な遺言書が作成されているときは、その内容に相続人は拘束されます。 そこで、もし遺言にて「夫が1/3、子どもが2/3の相...
- 公正証書遺言の証人になれるのはどんな人?手配の方法は?
専門家に依頼する場合、遺言書作成などと合わせた料金設定になっていることが多く、遺言書と証人で10万円からの料金設定をしている事務所が多くみられます。公証役場に紹介してもらう場合は、費用は公証役場によって異なりますが、6千円から1万円が相場となっています。まとめ今回は、公正証書遺言の証人になれるのはどんな人で、どの...
- 亡くなった方の孫が相続人になるケース|代襲相続の要件について
騙して遺言書を書かせた(または遺言の取り消しや変更をさせた)遺言書の偽造や変造、隠匿をした など しかし欠格となった人物の子(被相続人の孫)にそのような事由がなければ欠格とならず、欠格となった親に代わって孫が相続することができます。ケース③親が廃除されたケース②のように非常に悪質なケースでなくとも相続権が剥奪され...
- 遺産相続における有価証券・信託商品の移管・売却の手続きを解説
:遺言書・相続人・遺産の調査相続手続きの第一歩は「調査」です。 相続人の確定は、遺産分割協議を行う前提として必要不可欠です。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、相続人の範囲を正確に把握しましょう。 相続財産の調査では、故人が保有していた有価証券の種類や数量、取引していた証券会社を特定します。証券...
- 遺言書の「検認」が必要なケースと手続きの流れを解説
遺言書を見つけてもすぐに開封してはいけません。法律上、「検認」と呼ばれる手続きが必要とされているためです。遺言書を見つけたときの具体的な対応方法、検認の流れについてここで説明しておりますので、ぜひ参考にしてください。遺言書の検認とは検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するために行う手続きです。 家庭裁判所に遺言書を...
- 預貯金の残高証明の取得と解約の手続き~相続開始後の口座の扱い方~
相続人が遺産分割協議書または遺言書を用意し、金融機関に解約を申し出ます。口座は被相続人の死亡を金融機関が確認すると凍結されるため、解約手続きは凍結解除と同時に行います。※遺言執行者がいるときはその方が単独で手続きを行うことも可能。 このとき、遺言書に従い分配した場合には「遺言書(公正証書遺言または法務局に保管され...
よく検索されるキーワード
司法書士紹介

代表司法書士 武田一樹
私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。
当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?
お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。
-
- 所属団体
-
東京司法書士会(登録番号3502)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
-
- 経歴
-
平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
事務所概要
| 事務所名 | いつき司法書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502 |
| 電話番号 | 0422-24-7924 |
| FAX番号 | 0422-24-7925 |
| 受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
周辺マップ