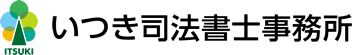遺産を渡す方法「特定遺贈」について| 包括遺贈や特定財産承継遺言との違いなど
遺産を渡す方法(あるいは遺産を受け取る方法)は複数あります。相続人であれば相続によって自動的に遺産を承継することができますし、そうでなくても遺言書により遺産を取得することができます。
遺言書を活用する場合にもさらに特定遺贈や包括遺贈などいくつかのパターンがあり、それぞれの効力について知り、最適な手段を選択することが重要といえます。ここでは特に「特定遺贈」に焦点を当てて、包括遺贈や特定財産承継遺言との違いにも触れつつ解説をしていきます。
遺産を渡す方法
遺産を渡す方法は大きく①相続と②遺贈の2つに分けられます。
相続は原則として法定相続人について発生するもので、法定相続人の範囲は被相続人であっても自由に広げることはできません。被相続人との関係性・立場に応じて定まるものです。
一方の遺贈については遺言書で自由に指定ができますので、親族でなくても遺贈により遺産を取得することは可能です。
相続
「相続」とは、亡くなった方の権利や義務を承継することを意味します。
単に現金や土地などの財産を受け取るだけでなく、権利者としての立場や債務者としての立場も受け継ぐこととなり、良い面も良くない面も広く含んでいます。
相続をする方のことは「相続人」と呼び、亡くなった方の配偶者や子などがまずはその権利を得ます。子がいなかったときは親へ、親もいないときは兄弟姉妹へと相続人になれる人物が変わってきます。
なお、相続は強制されるものではありませんので、相続による債務の負担が大きいときなどはその権利を放棄することも可能です。逆に、放棄をするための手続を行わなければ自動的に相続をしたものとして扱われてしまいます。
遺贈
「遺贈」とは、遺言に従い財産が贈られることを意味します。
遺言は法律に則り適式に作成された遺言書によって有効とされますので、遺贈が実行されるには遺言書の作成が欠かせません。
配偶者や子など、相続人となる予定の方に財産を渡したいのであれば何もしなくても相続により遺産は渡せますが、その他の人物に遺産を受け取ってほしいのなら遺贈を行う必要があります。そこで遺贈には手間がかかるという難点がありますが、相続人以外の誰に対しても自由に遺産を渡せるという強みがあります。
なお、遺贈は相続時に行う贈与のようなものであり、受け取りが強制されるものではありません。ただ、遺贈の種類によっては放棄をするのに手間がかかるケースもあれば、いつでも自由に放棄ができるケースもありますので注意が必要です。
特定遺贈とは
「特定遺贈」とは、上に掲げた遺産を渡す方法2つのうち、②遺贈に該当する行為です。
特に指定をせずまるごと渡すようなやり方ではなく、特定の財産を指定して行う遺贈が特定遺贈です。「この土地を譲る」「現金〇〇万円を譲る」など具体化された遺贈がこれに該当します。
特定遺贈を行うメリットは次の通りです。
- 遺贈の放棄はいつでもできる
- 遺贈に指定がない債務については負担を負わない
- 財産が特定されているため取得する内容をめぐってトラブルになりにくい
一方で、遺言書の作成から遺贈実行までの期間が長く空いていると、遺産の状態が変わっていて当初期待していた通りの受け渡しができないおそれがあります。また、良くも悪くも自由度が低いため遺産分割協議に参加して遺産の分割方法などについて口出しをすることはできません。
包括遺贈との違い
同じく遺贈の枠組みに入る「包括遺贈」と呼ばれる手法もあります。
こちらは特定遺贈とは異なり、財産の特定を行わず割合などで指定してする遺贈です。「遺産のすべてを譲る」「遺産の半分を譲る」などと遺言書に記載したときは包括遺贈となります。
包括遺贈は、遺言書作成時点から財産の構成が変化したとしても柔軟に対処できるという特徴を持ちます。例えば総資産2億円を持つ方が特定の人物に1億円相当の財産を与えたいと考えている場合、「現金1億円を譲る」との記載、「遺産の半分を譲る」との記載、どちらでも目的を果たすことができます。しかし前者の場合、遺言書作成後に1億円の現金で1億円相当の不動産を購入してしまうと、受遺者が1億円を受け取ることはできません。一方で後者では財産が形を変えていても遺産を受け取ることはできます。
このように柔軟に対応できるのが包括遺贈のメリットといえるでしょう。
しかしながら、債務など、マイナスの財産についてもその割合で取得することになりますのでこの点には注意が必要です。
まとめると両者の違いは次のようにまとめられます。
特定遺贈 | 包括遺贈 | |
|---|---|---|
遺贈の方法 | 遺言書に渡したい財産を特定して明記する | 遺言書で財産の特定は行わず、割合などで指定する |
債務の取得 | 指定がない限り取得しない | 指定の割合に応じて取得する |
遺産分割協議 | 参加しない | 参加する |
放棄の方法 | いつでも自由にできる | 遺贈について知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で申述の手続を行う (相続放棄と同様) |
特定財産承継遺言とは
遺言書を使って相続の方法を指定することもできます。
例えば「この建物を長男に“相続させる”」「預金〇〇万円を妻に“相続させる”」といった遺言を残すのです。これは「特定財産承継遺言」と呼ばれるもので、民法でも次のように定義されています。
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)
遺言書を使っているという点で遺贈と共通していますが、特定財産承継遺言はあくまで相続による遺産の授受を指定しているのであって、遺産を受け取れる人物も法定相続人に限られています。
遺贈との大きな違いとして「単独での登記申請が可能かどうか」が挙げられます。
不動産の名義が相続や遺贈によって変わるときでも、売買や贈与のときと同じく所有権移転の登記を行うことになるのですが、その際の手続が少し変わります。遺贈だと、受遺者は他の相続人の協力を得て登記申請を行う必要があるのですが、特定財産承継遺言であれば単独で登記申請ができます。他の相続人からの協力を得る必要がなく、スムーズに受け取りやすいのです。
どの方法を選択すべきか
どの方法で遺産の受け渡しを行うのが良いのか、それぞれに特性が異なりますので状況に応じた最適な選択をすることが大事です。
例えば不動産登記の手続を伴う場合であれば特定遺贈を行うよりも特定財産承継遺言により渡す方が取得者の負担を軽減できます。しかし取得する方が法定相続人でないのなら特定遺贈を行う必要があります。
他方、特定の人物に取得してもらう必要性がないのなら特に遺言書で指定を行わず相続により取得してもらうのでもかまいません。この場合、分割の方法などは相続人らの協議によって決定します。
もう1点、「放棄を行う可能性」についても考慮しましょう。特定遺贈であればいつでも放棄ができますし、そもそも債務の指定を行わなければ受遺者が借金を肩代わりするなどのリスクはありません。
一方、特定財産承継遺言や包括遺贈がなされていると、放棄をするのに家庭裁判所での手続が必要になるなど手間が大きいです。
よく検索されるキーワード
司法書士紹介

代表司法書士 武田一樹
私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。
当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?
お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。
-
- 所属団体
-
東京司法書士会(登録番号3502)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
-
- 経歴
-
平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
事務所概要
| 事務所名 | いつき司法書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502 |
| 電話番号 | 0422-24-7924 |
| FAX番号 | 0422-24-7925 |
| 受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
周辺マップ