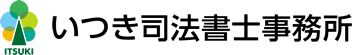遺産分割協議のポイント! 協議の準備や進め方、遺産分割協議書の作成方法について
相続手続の肝となるのが「遺産分割協議」です。親族間で揉める可能性があるのも遺産分割協議ですし、協議を始めるまでに必要な作業が多いなど、負担が大きいのも遺産分割協議です。また、法律に沿うことも重要であり、協議を始める前にはある程度知識を備えておくことが望ましいです。
当記事で遺産分割協議について解説し、準備すべきこと、協議の際のポイント、そして遺産分割協議書の作成についても説明していきます。
遺産分割協議を始めるために必要な情報
遺産分割協議を始めるには、「相続財産の内容」を把握する必要があります。また、協議の参加者となる「法定相続人」の範囲も調べておかないといけません。さらに、「遺言内容」も調べることで、話合うべき範囲が明らかになります。
まずはこれらの調査を進めていきましょう。
相続財産の内容
相続財産が明らかにならないと、遺産分割協議も進めようがありません。そこで、被相続人がどのような不動産を持っていたのか、有価証券は持っていたのか、預貯金の残高はどれほどか、など全財産について調査を進めていきます。
その際、負債についても必ずチェックしましょう。積極財産より借金などの消極財産が大きい場合は相続することが経済的なリスクとなります。明らかにリスクが大きいと判断できるときは「相続放棄」を検討します。
財産関係、権利義務関係が複雑で相続をすべきかどうかの判断が難しい場合は「限定承認」という選択を取ります。限定承認をした場合、仮に消極財産の方が割合大きかったとしても、弁済の責任は相続財産の範囲にとどめることができます。つまり、相続人個人の資産を換価したり、破産に追い込まれたりといったリスクを回避することができます。その分手続は大変ですが、検討する価値はあるでしょう。
法定相続人
相続財産の調査と同時進行で、法定相続人の調査も進めます。
調査方法は「被相続人の戸籍集め」が基本です。被相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍を集めていきます。そこに記された内容を読み取り、民法の規定に従って法定相続人になる人物を探していくのです。
配偶者は常に相続人になることができ、配偶者とともに①子ども、②親、③兄弟姉妹の順で基本的に相続人となる権利を得ます。判断が難しい場合や戸籍集めが難しいという場合は、司法書士など相続手続のサポートを行っている実務家を頼りましょう。
なお、相続放棄をした人物は法定相続人から除かれます。
遺言内容
遺言書が作成されているかどうかも調べなくてはなりません。もし、遺言書が存在しており、全財産についての承継方法等が記されていたときは、遺産分割協議が不要となります。遺言内容に従って財産を分ければ良いからです。
また、遺言内容には法的な拘束力もあります。相続人全員の合意があれば遺言に従わないこともできますが、原則として遺言内容に従った遺産分割を行います。
全財産について言及されていない場合、例えば財産の半分について指定がされているときは、残りの半分について遺産分割協議を進めることになるでしょう。
遺産分割協議のポイント
遺産分割協議を始めるときに押さえておきたいポイントがたくさんあります。以下にいくつかそのポイントを挙げていきます。
相続人全員による合意が必要
遺産分割協議は、最終的に「相続人全員の合意」が必要です。利害が対立することもあるかもしれませんが、最後は全員の協力が必要なのです。いつまでも頑なに同意をしない人物がいると、遺産分割協議を終わらせることができません。調停等、裁判所を利用することになります。
もちろん、1人の人物が勝手に分割方法を決めることも認められません。被相続人の配偶者、長男、その他どのような立場にある人物でも優位に立つことはありません。年長者も幼児も同格に扱われます。
法定相続分を基準に考える
「どんな割合で分けるべきかわからない」と悩むこともあるかもしれません。そのような場合は、法定相続分を基準にいったん検討してみると良いでしょう。
民法では相続人別の法定相続分が規定されており、その通りに分割しないといけないわけではありませんが、一応の取得割合が設けられています。
例えば配偶者と子どもが共同相続するとき、配偶者に1/2、子ども全体に1/2の割合が法定相続分として規定されています。配偶者と被相続人の親が共同相続するときは、配偶者に2/3、親全体に1/3が法定相続分です。
配偶者がおらず、同順位の法定相続人のみが共同相続するときは、人数で均等に分割することになります。
過去の贈与分も考慮する
法定相続分で分割するのが平等といえますが、過去に被相続人から贈与を受けていた場合、その分を考慮しないとバランスが取れないこともあります。
例えば被相続人の子ども2人が相続人になる場合、法定相続分はそれぞれ均等に1/2です。遺産総額1億円であればそれぞれ5,000万円ずつで分割ということになります。
しかしながら、相続前に一方が4,000万円自宅の贈与を受けていた場合、5,000万円ずつの分割が平等とは言い切れません。その贈与がなければ遺産総額1億4,000万円であり、法定相続分に従うとそれぞれ7,000万円取得できたことになります。
この考え方を「特別受益の持ち戻し」といいます。
生前に被相続人から特別の利益を受けているのならその分を相続財産に含めて再計算する、ということを意味します。
ただし、法的に特別受益であることの評価を受けるのは難しく、過去に贈与を受けたからといってそのすべてが特別受益として認められるわけではありません。
不動産の分割方法と配偶者居住権の検討
相続財産に不動産が含まれているときは遺産分割の方法で困ったり揉めたりするリスクが高まります。
分割方法を別途考えず法定相続分で相続してしまうと「共有」状態となり、物件の管理・処分で後々困ることになります。そこで、できるだけ別の方法で分割することが一般的には推奨されています。共有以外には、具体的に次の3つの分割方法が挙げられます。
現物分割 | 土地や建物をそのままの形で分けること。 家屋Aは配偶者に、倉庫Bは長男に、土地Cは長女に、といった形で分ける。シンプルな分割方法で手続も簡単。ただし相続財産の価格を平等にするのが難しくなる。 |
|---|---|
換価分割 | 不動産を売却することで得た金銭を分けること。 誰も不動産を取得せず、現金という形で平等に分けることが可能となる。相続税の納税資金対策にもなる。ただし売却に手間と時間がかかること、相続税の負担が増す可能性があるなどの問題がある。 |
代償分割 | 不動産を取得した人物が代償金をその他の相続人に支払うこと。 不動産を遺すことができ、相続財産の価格も平等にすることができる。ただし現金の負担は大きい。 |
相続税の問題も絡んでくるため、税理士の助言も受けておくと良いでしょう。
なお、残っている不動産が被相続人の自宅であって、そこで配偶者が同居していたというケースも考えられます。このとき配偶者は自宅で住み続けるため自宅を相続することになるでしょう。しかし、自宅という大きな財産を取得することで、生活資金となる預貯金などが十分に確保できないおそれがあります。
仮に2,000万円の価値を持つ自宅と預貯金2,000万円があった場合、配偶者が自宅を相続、子どもが預貯金を相続すると、配偶者は一切の預貯金が取得できません。
こういった場合に備えて近年設けられたのが「配偶者居住権」です。自宅を①居住権と②負担付き所有権に分けることで生活費問題の解決を図るのです。2つの権利に分ければ、①を取得する配偶者も自宅の価格をまるまる相続することにはなりません。その分預貯金も取得できることになります。
相続税対策を取ること
遺産の分け方で揉めていない場合、相続税にも目を向けると良いです。税負担を軽減するために最良な分割方法とは何か、税理士に相談して検討を進めましょう。
その際、二次相続の考慮も必要です。被相続人の配偶者が相続人にいて、その方が高齢であるなど、近いうちに二次相続が起こる可能性があるのなら、現在の相続と将来の相続を見越した相続税対策を取ります。
例えば配偶者控除をフルに活用すれば現在の相続税の負担は小さくすることも可能です。しかしながら、配偶者控除の使えない二次相続で大きな財産を子どもが取得することになり、結果として全体で見ると税負担が増してしまうというケースもあるのです。
相続税の仕組みを熟知した税理士にアドバイスを求め、節税効果の大きな遺産分割方法も考えてみましょう。
遺産分割協議書の作成
遺産分割の内容が固まれば、「遺産分割協議書」を作成しましょう。
書面にまとめることは法律上の要件ではありません。これを作成しなくても遺産分割協議は有効です。しかしながら、遺産分割協議が有効であることを対外的に示すためにも、実務上は必須の手続であると捉えておくべきです。
各種財産の名義変更手続、金融機関での手続の際も、遺産分割協議書の提示が求められます。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書を作成するにあたり知っておきたい知識を以下にまとめます。
フォーマットの指定はない
遺産分割協議書は、そもそも作成自体が義務ではありませんので、作成方法についても決まりはありません。どんな形で作成をしても違法にはなりません。
書式も用紙のサイズも自由ですし、手書きでも、パソコンを使って作成するのでもかまいません。とはいえ、あえてオリジナルの遺産分割協議書を作る必要もありません。見やすく、どの窓口に提出するときでもスムーズに手続を進められるよう、一般的な遺産分割協議書の書き方に寄せると良いです。
よくあるのは次のような構成から成る遺産分割協議書です。用紙上部の記載事項から順に示します。
- 被相続人に関する情報
- 前文
- 各人の相続する財産の情報
- 相続人間で別途定めるルール
- 後文
- 作成日付
- 相続人に関する情報と各々の署名・実印
当事者に関する記載事項について
遺産分割協議書を作成するなら、少なくとも「被相続人に関する情報」「相続人に関する情報」は記載しましょう。
被相続人に関する情報としては、氏名・生年月日・死亡日・本籍地を載せると良いです。
----- 記載例 ----
被相続人:〇〇 〇〇 (令和○年○月○日死亡)
生年月日:昭和○年○月○日
本籍地:〇〇○○
---------------------
被相続人に関する情報としては、氏名・住所など、人物の特定ができる情報を載せると良いです。相続人全員分を記載し、各々実印で押印もしましょう。
----- 記載例 ----
氏名:〇〇 〇〇 ㊞
住所:〇〇〇〇
氏名:〇〇 〇〇 ㊞
住所:〇〇〇〇
:
---------------------
また、遺産分割協議書を作成した日付の記載も重要です。
相続財産に関する記載事項について
分割した財産についての情報も記載しなければ意味がありません。各財産について記載するときのポイントは、「どの財産について言及しているのかがわかるように特定すること」と「その財産をどれだけ取得したのかがわかること」です。
例えば土地を相続するのであれば、所在・地番・地目・地積を正確に記載します。その際、権利証や登記簿謄本を参考にしましょう。
預貯金については、銀行名・支店名・種目・口座番号・金額を事実とずれのないよう慎重に記載します。
債務についても詳細に情報を書き記し、特定ができるようにすべきです。債権者名・契約内容・残債務など、契約書等を参考に記載していきます。
遺産分割協議書の作成方法についてお悩みの場合は、司法書士や弁護士、行政書士などを頼りましょう。
よく検索されるキーワード
司法書士紹介

代表司法書士 武田一樹
私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。
当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?
お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。
-
- 所属団体
-
東京司法書士会(登録番号3502)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
-
- 経歴
-
平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
事務所概要
| 事務所名 | いつき司法書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502 |
| 電話番号 | 0422-24-7924 |
| FAX番号 | 0422-24-7925 |
| 受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
周辺マップ